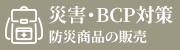温度センサー(サーミスタ)実測試験について
- 2024/10/15 更新

今回ご紹介するのは、恒温槽を使用した計測機器部品の検査についてです。
今回検査を実施したのは温度を計測する”温度センサー”でしたが、およそセンサーと呼ばれる類の検査でその健全性や動作確認をする場合によく用いられる方法が、 疑似的に測定環境を作り出し、その中で実際にセンサーを動かすことです。 温度センサーでいえば、25℃の環境下でセンサーも同じ温度を示せばその製品は良品であると判断できるわけです。
そうは言っても、空気の対流する室内で一定の温度を保ち続けることは非常に困難です。 エアコンのPRとして「お部屋をまんべんなく暖め(冷やし)ます」といった点をセールスポイントとして各メーカーがこぞって打ち出すのは、 室内で一定の温度を保ち続けることの難しさの裏返しであるとも言えます。
そこで登場するのが今回検査に使用した恒温槽です。 恒温槽とは設定した温度を長時間一定に保ち続けられるように制御された機器です。 今回使用したタイプは、内部に検査品を設置できる広さの内部空間を備えたものでした。
検査内容としては、ケーブル接続した温度センサーを恒温槽の中に設置し、温度センサーに接続した測定器(表示器)が示した値を検査表に書き記し、 その製品の精度範囲内に収まっているかを確認していきます。 検査項目はさほど多くは無いため、作業としての難易度はそれほど高くはありません。 しかし製品の出し入れ時の扉の開閉により恒温槽内部に室内の空気が流入するため、せっかく一定に保たれていた温度が影響を受けてしまい、 再度安定するまでに若干の時間を費やします。 加えて作業件数が多かったため、いかに効率よく作業を進めるか、何も手が付けられない待ち時間をどれだけ短くできるか、といった点が求められる作業だと感じました。 幸い、私の検査時には先行して作業を進めていた先輩検査員が試行錯誤の末に辿り着いた最短検査への最適解が既に用意されていたため、 その作業手順を順守することで何とか検査を進めることができました。 この時は、会社内部での情報共有や、経験やノウハウの継承といった点のありがたみを実感しました。
さて、今回は「温度」の疑似環境を再現するための「恒温槽」でしたが、もちろんセンサーや計測器の種類によっては様々な機器が必要となってきます。 例えば「酸素計」や「ガス分析計」ではそれぞれに適した組成のガスと検査設備が必要となってきます。 コンテックでは、長年にわたる電子機器、計測機器、精密機器などの校正・修理・点検・検査業務により培った豊富な経験とノウハウとを活かした 質の高い丁寧な製品検査によって貴社の業務をサポートいたします。 是非、お気軽にお問合せください。
イプロス特設サイト掲載中!
| <出荷検査サービス> | <筐体設計・製作> | <ハードケース販売> | <BCP対策> | |
 |
 |
 |
 |
|
| <防災・災害対策> | <ケーブル点検・修理> | <精密機器点検・検査> | <校正サービス> | |
 |
 |
 |
 |
|
| <イプロス特設サイト> | ||||
|
||||
「B to B」向けデータベースサイトで、当社がご提供する
サービスや取扱い製品などの情報を発信しています。