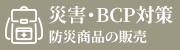コスト削減!高価なのに酷使され断線するケーブルは修理で復活
- 2025/02/13 更新

今回は「衝撃吸収試験」に使用されるケーブルの修理についてお話しいたします。
衝撃吸収試験とは?
衝撃吸収試験は、物体が衝撃を受けた際にその衝撃エネルギーをどの程度吸収できるかを評価する試験です。 みなさんもCMや動画などで、搭乗者の代わりにダミー人形を乗せた乗用車が壁に衝突する実験や試験の映像を見たことはありませんか? この試験は様々な製品や材料に対して行われ、前述の車をはじめ、身近なものではヘルメットやスマホケースなど、 特に安全性や保護性能が重要視される分野で使用されます。
衝撃吸収試験に必須の加速度センサー
衝撃吸収試験において、加速度センサーは非常に重要な役割を果たします。 加速度センサーは、試験中に物体に加わる力や加速度を検出して衝撃の強さや持続時間を正確に測定します。 その結果を各分野や製品ごとに規定された値と比較して、求められる安全性や品質を満たしていることを確認するのです。
例えば、自転車用ヘルメットの衝撃吸収試験においては
- 300 G(2,942m/s2) 以上の衝撃加速度を生じないこと.
- 150 G(1,471m/s2) 以上の衝撃加速度を生じた場合は,その継続時間は4ms以下であること.
といった規定が明記されており、この文言からも「加速度」と「持続時間」が重要なデータであることが伺えます。
避けられないケーブルの断線
試験に使用される加速度センサーは、試験対象に取り付けられるセンサー感応部と、センサー感応部が検出した信号値を受信して表示・記録する表示器本体とに分かれ、 それらはケーブルによって接続されます。 衝撃吸収試験では、高所から試験対象を落下させて衝撃を与える落下試験機や、試験対象に振動を加えて衝撃や振動耐性を評価する振動試験機などの 衝撃を与えるための装置を設定し、テストする製品や材料を装置にセットして規定された条件下で、試験対象に衝撃を与えます。 検査の結果によっては試験対象が破損や損傷することもあるため、試験対象に取り付けられたセンサーやケーブルにも相応の負荷がかかります。 加速度センサーに使用されるケーブルは、その使用環境に対応するために芯線を耐久性のあるシールドなどで覆っていますが、それでも断線は発生してしまいます。 ケーブルには試験結果に影響を及ぼさないだけの柔軟性や軽さも必要なため、いたずらに太くしても重量増となったり、 強くて硬い材質を採用しても柔軟性が低下するなどの懸念から、現行製品の仕様に落ち着いているものと考えられます。
無線ではダメなの?有線と無線のメリット・デメリット
形あるものはいつか壊れる…のは世の常ですが、それならば形のあるケーブルを用いない通信手段(=無線式)ならどうでしょうか。 およそ計測器というものは、おおまかにセンサー感応部とセンサーからの信号値を受信して表示する表示器、そしてそれらをつなぐケーブルから成り立ちます。 機器同士をつなぐ方法としては有線ケーブルを使用しない無線式もありますが、有線と無線にはそれぞれのメリットとデメリットがあります。 以下にそれぞれの特徴を挙げてみましょう。
有線測定
- 信頼性: ケーブルを使用するため、データの送受信が安定して行われます。外部の干渉が少なく、ノイズによる影響も受けにくいです。
- 高速伝送: 一般的に、有線接続の方が高速なデータ伝送が可能です。大量のデータや高い精度を求める場合に適しています。
- 範囲の制約: ケーブルの長さに制約があるため、長距離のデータ送信には不向きです。設置場所の柔軟性も限られます。
無線測定
- 利便性: ケーブル不要で設置が容易。移動や再配置が簡単に行えます。
- 柔軟性: 多数のデバイスを同時に接続でき、広範囲のデータ収集が可能です。遠隔地のデータ収集にも適しています。
- コスト削減: ケーブルや配線工事の必要がないため、初期コストや設置コストが抑えられます。
- 干渉と遅延: 環境によっては電波干渉や遅延が発生することがあります。特に金属構造物や他の電波源が多い場所では影響を受けやすいです。
以上のように、有線と無線ではそれぞれにメリットとデメリットがありますが、衝撃時の一瞬のデータをより正確に高い精度で取得することを優先するのであれば、 有線式の優位性が勝ります。実際に当社に修理依頼を頂いたメーカーでは、有線ケーブルを使用した衝撃吸収試験を実施されていました。
断線したケーブルはもう廃棄するしかない?
加速度センサーに使用される接続ケーブルは高価になる傾向がありますが、衝撃吸収試験で断線するたびに新品ケーブルへの交換となると、 製品の安全性や品質のためと理解していても、企業や品質管理の担当者としては嵩むコストに頭を悩ませているかもしれません。 しかし、そこで破損ケーブルを廃棄する前に一度検討していただきたいのが"断線箇所の修理"です。 破損状態によりますが、切れてしまった芯線(電線)をはんだ付けすることで再び導通可能状態に戻すことが可能です。 当社では各種ケーブルの修理実績がありますので、お気軽にご相談ください。 コネクタの破損もコネクタ部分の入手が可能であれば、交換が可能です。
一度切れたケーブルを元の強度に保つ工夫
切れた電線(芯線)を修復することで、ケーブルの「電気を通す」「電気信号を伝える」という機能に関しては回復が可能です。 ケーブルの設置環境が電子機器の内部に収納されケーブル自体に過度な応力や振動などがかからないことが前提のケースでは、 はんだ付け後に熱収縮チューブなどで絶縁処理をして修理完了となります。 しかし、今回の例として挙げている加速度センサーのようにケーブル自体に衝撃の負荷が掛かることが想定されるケースでは、 そのまま完了とするには不十分と思われます。
一般的なケーブルの構造は、電気を通す「導体」である複数本の電線を、電気を通さない「絶縁体」と「外皮(シース)」で覆ったもので構成されます。(図1参照)

中心の電線(芯線)をはんだ付けしただけの状態では、断面積において大部分を占める外皮(シース)や絶縁体が無いため、 ケーブルに負荷がかかった際には細い電線(芯線)のみでその負荷に耐えなければなりません。 太さや強度に偏りがある物体は、負荷がかかった際に弱い箇所に応力が集中するため、このままでは元の状態よりも破損しやすいケーブルとなってしまいます。(図2参照)

そこで当社では、補修箇所に応力が集中しないように補強を追加することで問題をクリアしています。 補修箇所のみを強化してしまうと今度はその境目に応力がかかるため、補強の材質なども吟味し、応力に対して出来るだけフラットに負荷が分散されるように補修しました。
ケーブルの修理は㈱コンテックまで
東京・埼玉・神奈川・千葉を含む、首都圏近郊に位置する当社では、計測器に使用されるLEMO(レモ)ケーブルやBNCケーブルなどの各種ケーブルをはじめ、 精密機器などの様々なケーブルを取り扱っております。 1978年の創業より電子機器、計測機器、精密機器などの修理・点検・校正・検査業務を通じて多種多様なケーブルの取り扱い実績のある弊社は、 長年にわたるノウハウと実績を活かした高品質で丁寧な各種ケーブルの修理から、製作、検査、点検までの幅広いサービスを提供いたします。関連ページ
ケーブル修理関連ページ ▼
|
ケーブル修理関連ページ ▼
|
イプロス特設サイト掲載中!
| <出荷検査サービス> | <筐体設計・製作> | <ハードケース販売> | <BCP対策> | |
 |
 |
 |
 |
|
| <防災・災害対策> | <ケーブル点検・修理> | <精密機器点検・検査> | <校正サービス> | |
 |
 |
 |
 |
|
| <イプロス特設サイト> | ||||
|
||||
「B to B」向けデータベースサイトで、当社がご提供する
サービスや取扱い製品などの情報を発信しています。